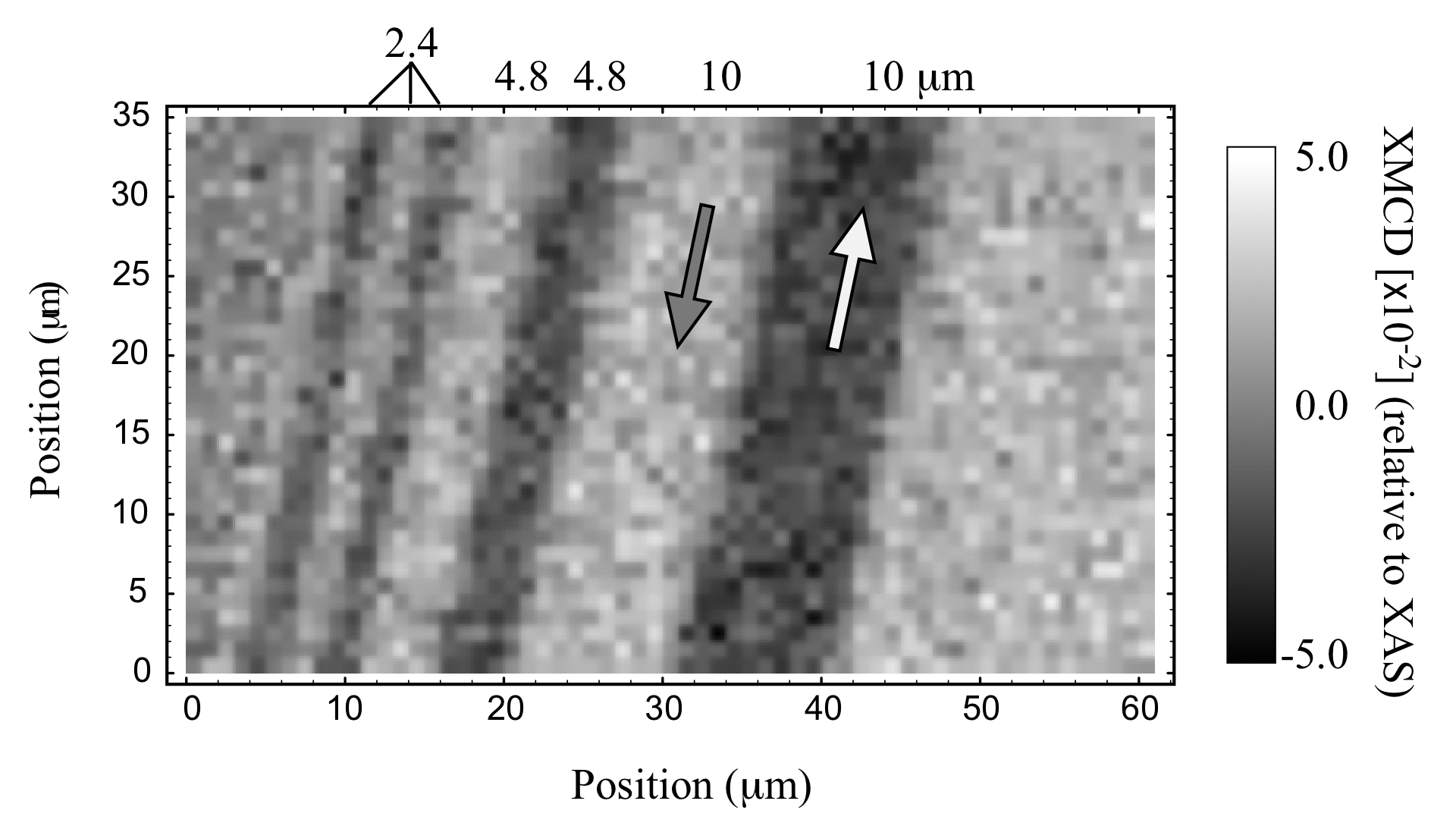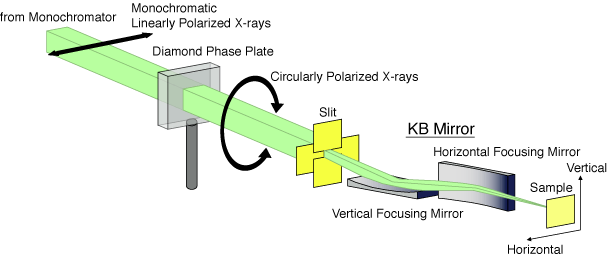走査型X線磁気顕微鏡
問い合わせ番号
SOL-0000001608
ビームライン
BL39XU(X線吸収・発光分光)
学術利用キーワード
| A. 試料 | 計測法、装置に関する研究 |
|---|---|
| B. 試料詳細 | 磁性体 |
| C. 手法 | 吸収、及びその二次過程 |
| D. 手法の詳細 | XAFS, XANES, MCD, LD |
| E. 付加的測定条件 | 偏光(円、楕円), マイクロビーム(1-10μm), 二次元画像計測, 磁場(< 2 T), 室温 |
| F. エネルギー領域 | X線(4~40 keV) |
| G. 目的・欲しい情報 | スピン・磁性構造 |
産業利用キーワード
| 階層1 | 記憶装置 |
|---|---|
| 階層2 | HD、MO |
| 階層3 | 磁性層, 磁気ヘッド, スピンバルブ膜 |
| 階層4 | 磁化, 磁気異方性, 界面磁気構造 |
| 階層5 | XAFS, XMCD, イメージング |
分類
A80.14 磁性材料, M40.30 磁気吸収
利用事例本文
走査型X線磁気顕微鏡は、試料に含まれる個々の磁性元素について2次元磁気画像計測を行うことのできるユニークな装置です。得られる画像の空間分解能はおよそ2 mです。この方法は、3d遷移金属元素、希土類元素、5d貴金属元素を含む磁性体試料に適用できます。また、試料上のm程度の大きさの領域について、X線磁気円二色性 (XMCD) スペクトルやXAFSスペクトルを測定することができます。
図に示すのは、CoCrPtB面内磁化膜について測定した2次元磁気画像です。あらかじめ縞状の磁気パターンが記録された試料を持ちいました。この例では、X線のエネルギーをPtのL3吸収端 (11.56 keV) に合わせ、試料中のPtの磁化の大きさや向きに応じた濃淡を観測しました。最小2.4 m幅の磁気パターンまで解像できています。
図. 走査型X線磁気顕微鏡で測定した、CoCrPtB面内磁化膜の2次元磁気画像
画像ファイルの出典
所内報
誌名
ナノテクノロジー総合支援プロジェクト研究成果報告書 Vol.4, 2004年A
ページ
p. 147
測定手法
走査型X線磁気顕微鏡は、ダイヤモンド移相子とX線用の集光ミラー (KBミラー) による光学系から成ります。移相子で生成した円偏光X線を、KBミラーを使って試料上で2 m 程度のスポットに集光します。円偏光の向きを切り替えながら試料からの蛍光X線強度をモニターすることで、ビーム位置での試料のX線磁気円二色性 (XMCD) 信号を測定します。このXMCD信号から、試料の磁化の大きさや磁化の向きに関する情報が得られます。試料の位置を精密ステージで動かすことで試料上でのX線ビーム位置を走査し、2次元画像を得ます。
図. 走査型X線磁気顕微鏡の光学系
画像ファイルの出典
所内報
誌名
ナノテクノロジー総合支援プロジェクト研究成果報告書 Vol. 4, 2004年A
ページ
p. 146
測定準備に必要なおおよその時間
3 シフト
測定装置
| 装置名 | 目的 | 性能 |
|---|---|---|
| 走査型X線磁気顕微鏡 | 2次元磁気画像の測定、微小領域におけるXMCD測定 | 集光X線スポットサイズ 2ミクロン、光子数~10^10 photons/s |
参考文献
| 文献名 |
|---|
| M. Takagaki, M. Suzuki, N. Kawamura, H. Mimura, and T. Ishikawa, The 8th International Conference on X-ray Microscopy (XRM2005), 26-30 July 2005, Himeji, Japan. |
関連する手法
磁気力顕微鏡(MFM), 光電子顕微鏡 (PEEM), 透過型X線顕微鏡
アンケート
SPring-8だからできた測定。他の施設では不可能もしくは難しい
本ビームラインの主力装置を使っている
最近2年以内に導入した装置を使った事例
測定の難易度
初心者でもOK
データ解析の難易度
初心者でもOK
図に示した全てのデータを取るのにかかったシフト数
2~3シフト