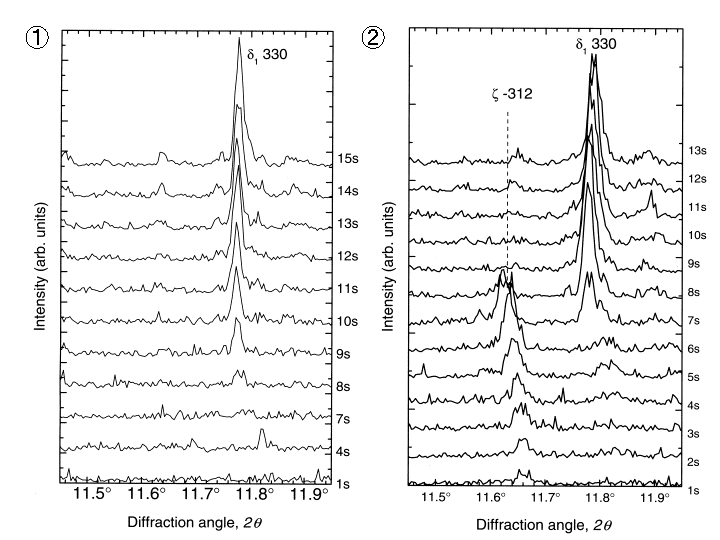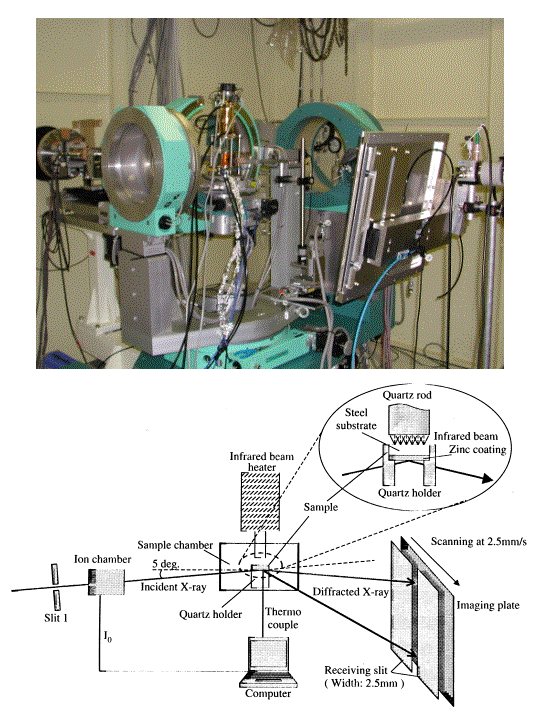溶融亜鉛めっき鋼板の合金化反応過程のin-situ観察
問い合わせ番号
SOL-0000001402
ビームライン
BL19B2(X線回折・散乱 II)
学術利用キーワード
| A. 試料 | 無機材料 |
|---|---|
| B. 試料詳細 | 金属・合金 |
| C. 手法 | X線回折 |
| D. 手法の詳細 | 広角散乱 |
| E. 付加的測定条件 | 高温(〜500度), 時分割(比較的遅い) |
| F. エネルギー領域 | X線(4~40 keV) |
| G. 目的・欲しい情報 | 構造変化 |
産業利用キーワード
| 階層1 | 機械, 金属, 建設, 工業材料 |
|---|---|
| 階層2 | 構造材(鉄、非鉄) |
| 階層3 | 被膜、潤滑剤 |
| 階層4 | 表面・界面, 結晶構造, 配向 |
| 階層5 | 回折 |
分類
A80.20 金属・構造材料
利用事例本文
本事例では溶融亜鉛めっきの合金化過程についてin-situ X線回折実験を行い、合金化過程初期(~数10sec)の亜鉛めっきからのX線回折パターンの時間変化を解析しました。このデータから、合金化過程のZn-Fe合金相の成長パターンのめっき組成依存性が明らかになりました。
亜鉛めっき合金化過程初期のX線回折パターンの時間変化
①Al0.13%添加亜鉛めっき ②純亜鉛めっき
[ A. Taniyama, M. Arai, T. Takayama and M. Sato, Materials Transactions 45, 2326-2331 (2004), Fig. 4, 7,
©2004 日本金属学会 ]
画像ファイルの出典
原著論文/解説記事
誌名
A. Taniyama, M.Arai, T. Takayama and M. Sato, Material ransaction Vol.45, No.7 (2004) pp.2326-2331
図番号
Fig.4,Fig.7
測定手法
この測定では亜鉛めっき鋼板試料を回折計の上で赤外線導入加熱炉で加熱(~460℃)しながらX線回折パターンの時間変化を観察しました。X線回折パターンは縦長のスリット(2.5×400mm)で1次元に切り出したものをイメージングプレート(IP)に記録し、さらにさらにIPを水平方向に移動することでその時間変化を連続的に記録しました。SPring-8の特徴である高エネルギーX線(28KeV)を用いることで、めっきと鉄鋼板界面で生じるZn-Fe合金化反応過程の初期過程(~10sec)を時間分解能1秒程度で観測することに成功しました。
実験装置のレイアウト写真(上)と概念図(下)
[ A. Taniyama, M. Arai, T. Takayama and M. Sato, Materials Transactions 45, 2326-2331 (2004), Fig. 1,
©2004 日本金属学会 ]
画像ファイルの出典
原著論文/解説記事
誌名
A. Taniyama, M. Arai, T. Takayama and M. Sato, Material Transactions, Vol. 45, No. 7 (2004) pp.2326-2331
図番号
Fig.1
測定準備に必要なおおよその時間
9 シフト
測定装置
| 装置名 | 目的 | 性能 |
|---|---|---|
| 多軸回折計 | X線回折の測定 | IPカメラ搭載時、可能なカメラ長は40~80cm |
| IPカメラ | 回折パターンの時間変化の記録 | IPの記録面積200×400mm |
参考文献
| 文献名 |
|---|
| Akira Taniyama, Masahiro Arai, Toru Takayama and Masugu Sato, Material Tranzaction, Vol. 45, no. 7 (2004) p2326-2331 |
関連する手法
アンケート
SPring-8だからできた測定。他の施設では不可能もしくは難しい
本ビームラインの主力装置を使っている
ユーザー持ち込み装置を使った
測定の難易度
熟練が必要
データ解析の難易度
中程度
図に示した全てのデータを取るのにかかったシフト数
4~9シフト